|
ブックレビュー |
| 2014年3月9日 |
本書は、中国共産党の民族政策とモンゴル人アイデンティティとの間で苦悶(くもん)し続けたウラーンフー(中国名は烏蘭夫)という一人の政治リーダーの半生を跡付けることで、中国現代史の再解釈を試みようとする野心作である。ソ連留学組のウラーンフーは中国共産党に協力して内モンゴルを治め、いち 早く内モンゴル自治区を創設した。そうした経緯もあり、かれは新中国建国後も共産党の最高幹部の一人となり、民族融合のシンボル的存在となった。
(岩波書店・2400円 ※書籍の価格は税抜きで表記しています)
中華人民共和国成立4年前の1945年4月、毛沢東は少数民族の自決を認め、将来の国家像に関しても「中華民主共和国連邦」とすら語っていた。しかしその後この部分は抹消され、連邦制も否定された。著者によれば、ウラーンフーはこの言葉を信じ、中華民族の一体化を図った国民党ではなく、民族の自決や自治に 対してより柔軟な姿勢を取るかに見えた共産党に協力した。
しかし、ウラーンフーのそうした夢は現実の中でもろくも潰(つい)えていった。清末から内モンゴルへの中国人移民は急増し、建国直後の漢族対モンゴル族の比率ではすでに漢族が圧倒していた。この現実の中で、農耕開発至上主義の漢族 と、牧畜と自然を重視するモンゴル族との矛盾は拡大し、ウラーンフーも抵抗したが、結局は多数支配に屈した。
文化大革命において、かれは 大漢族主義反対を推し進めて民族分裂をはかり独立王国を創ろうとしたとの理由で激しく攻撃され、文革後になってようやく名誉回復された。文革を利用して、ウラーンフーをはじめモンゴル族を打倒し、内モンゴルの自治を形骸化させることが共産党の意図であったと著者は言う。
本書は、体制内改革 の可能性に身を投じて内モンゴルの主体性を確保しようとした一人のモンゴル族リーダーの苦悩と挫折を描いた鎮魂歌である。ウラーンフーという人物に著者自身の情念を投影しすぎた感があるのと、共産党側の分析にやや物足りなさを感じるが、本書を通して、読者にとっては「中国」あるいは「中華」の意味を改めて 問い直す契機となるにちがいない。
(防衛大学校長 国分良成)
[日本経済新聞朝刊2014年3月9日付]
http://www.nikkei.com/article/DGXDZO67986960Y4A300C1MZA001/


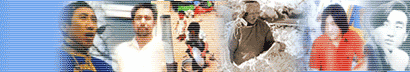


 Beyond
Great Walls: Environment, Identity, and Development on the Chinese
Grasslands of Inner Mongolia
Beyond
Great Walls: Environment, Identity, and Development on the Chinese
Grasslands of Inner Mongolia China's
Pastoral Region: Sheep and Wool, Minority Nationalities, Rangeland
Degradation and Sustainable Development
China's
Pastoral Region: Sheep and Wool, Minority Nationalities, Rangeland
Degradation and Sustainable Development The
Ordos Plateau of China: An Endangered Environment (Unu Studies on
Critical Environmental Regions)
The
Ordos Plateau of China: An Endangered Environment (Unu Studies on
Critical Environmental Regions)